|
 誰もが認める世界最高のギタリスト 誰もが認める世界最高のギタリスト
かのエアロスミスがビッグになり、ライブでベック時代のヤードバーズの曲「トレン・ケプト・ア・ローリン(ストロール・オン)」を演奏したとき、ベックが急遽ゲストでステージに上がるや、ジョー・ペリー(g)は感動で涙を流しながらその場に立ちつくした。
ジェフ・ベックは、エリック・クラプトンと共に天才ギタリストとして60年代半ばから活躍しながら、性格やギターに対する姿勢はまったく違っていた。"神様"と呼ばれながらも、常にフレンドリーで誰よりも人間的であったクラプトンに対し、ベックは性格も利己主義で自分勝手、非情だとまで言われ、どこか近寄りがたい存在であった。ギター奏法においても、かなり独創的でトリッキーなことから、後継者になるようなプレイヤーも現れず、いつしか「孤高のギタリスト」と呼ばれるようになっていた。
しかし、それにも関わらず、ギタリスト達の間で未だにカリスマ的な人気を保っているのは、やはり他の追随を許さないテクニックとセンス、並々ならぬギターへの情熱が伝わってくるからであろう。ジャンルを無視したミュージシャン達が選ぶギタリストの人気投票でも、ベックが最も活躍していた70年代には、ジャズやブルース・プレイヤー達を押さえてずっと1位に君臨していた。
これだけの人気者、本来なら誰もがそのテクニックをマネし、取り入れたがるはずだ。しかし、そう簡単にベックのギターをマネすることはできない。大のベック・ファンであるジョー・ペリーでさえ、ベックの弾き方とはまったく違うスタイルであるし、記憶にある限りでも、ベックのスタイルを大胆に取り入れているのは、ジミ・ヘンドリックスとゲーリー・ムーア、TOTOのスティーヴ・ルカサー、それに元ディテクティヴのマイケル・モナークぐらいのものだ。凡人の自分などは、昔ギターを弾いていた頃、いったいどうやって弾いているのかさえわからないほどだった。
常識を超えた職人芸的プレイ
1944年6月24日生まれ、イギリスのサリー州ウェリントン出身のジェフ・ベックは、18歳の頃からバンドを結成し、主にジーン・ヴィンセントやエディ・コクランなどの曲をレパートリーにしていたという。またその頃、妹の紹介でジミー・ペイジ(g)とも出逢っている。63年にはオール・スターズというバンドに参加し、ニッキー・ホプキンス(key)らに混じって初レコーディングを体験した。その直後、トライデンツというバンドを結成し、ジミー・ペイジやロン・ウッドのバンドの前座を務めたこともある。また、この頃にはすでにフィード・バック奏法を編み出したり、レス・ポールから影響を受けたと思われるトリッキーなプレイで、かなり評判になっていた。
そんなある日、ジミー・ペイジの紹介でヤードバーズのギタリストへ誘われる。そして65年にエリック・クラプトンの後釜としてヤードバーズへ正式加入した。
しかしこの頃のベックは病気がちで、たびたび代役にジミー・ペイジが入るようになり、一時はツイン・リード・ギター体制になるが、まもなくベックは脱退。66年にはプロデューサーのミッキー・モストとソロ契約を交わしている。
この頃になると、ベックはすでにジミ・ヘンドリックスが「クラプトンとベックに会わせてあげるから…」という誘いにのって渡英したというぐらいの有名人であった。ジミが派手にプレイして有名になったフィード・バック奏法や大胆なアーミング・アプローチ(ギターに付いているトレモロ・アームという音程を変える装置を使ったプレイ)、ピック・ポルタメント(弦の上をピックでギィーっと滑らせる奏法)も、すべてベックの奏法を取り入れたものだ。
67年には、ソロとしてベック自ら歌も唄っているシングル「ハイ・ホー・シルヴァー・ランニング」を発表。これが全英14位の大ヒットとなり、続けて「タリー・マン」「恋は水色」のシングルもスマッシュ・ヒットさせた。
68年になると、ソロ時代のバック・メンバーを中心に、ジェフ・ベック・グループを結成。そのメンバーの中には、ロッド・スチュワート(vo)、ロン・ウッド(b)、エインズレー・ダンバー(ds)、ニッキー・ホプキンス(key)らがいた。
このバンドはベックのわがまま(音楽的なもの)で、メンバーをコロコロ代えつつ2枚のアルバムを残し、69年のウッドストック・フェスティバル出演間際に突然解散した。すぐさまロッドを残しつつ、元ヴァニラ・ファッジの2人、ティム・ボガート(b)とカーマイン・アピス(ds)を引き入れてニュー・バンドを結成しようとするが、ベック自身が交通事を起こし重体となってしまったため実現しなかった。
70年、事故から立ち直ったベックは、数々のセッションに参加するうちに、若き敏腕ドラマーのコージー・パウエルと出逢う。翌年にはそのコージーや、以降ベックの音楽にはコンポーザーとして欠かせない存在になるマックス・ミドルトン(key)らジャズやR&B系のミュージシャンを集め、第2期ジェフ・ベック・グループを結成。すばらしく進化を遂げたサウンドで周囲を驚かせた。しかし、その変化は、かならずしも好意的にばかり受け取られたわけではなく、昔からのベック・ファンの中には、離れていく人も少なくなかった。そのサウンド変化とは、ジャズやR&B色を強く打ち出した、スティーリー・ダンなどとも共通するフュージョン的なもの(もっと黒っぽいが)であったのだ。このバンドでも2枚のアルバムをリリースし、セカンドの方は全米15位と、まずまずのセールスを記録した。
その後、コージーが脱退したのを機に再びティム・ボガートとカーマイン・アピスに接触。72年ついにこの2人を入れた念願のバンドBBAを結成した。この時、第1期ジェフ・ベック・グループのメンバーであったロッド・スチュワートは、ティムとカーマインに、「ジェフとはやめた方がいい、つぶされるぞ…」と忠告したらしい。しかし、彼らはこのことについてのインタビューで、「だってあのジェフ・ベックから誘いを受けたんだぜ!」と興奮気味に語っていた。
73年にはこのBBAで来日も果たし、ロック史上に残るパフォーマンスを繰り広げたが、案の定アルバム2枚をリリースしただけでBBAは解散。カーマインは結局その後ロッドのバック・バンドにおさまっている。
ちょうどその頃、ローリング・ストーンズからギターのミック・テイラーが脱退し、ベックを代わりにという誘い話もあったらしいが、「あんな3コードばっかりやってる退屈なバンドはゴメンだ」とベックが言ったとか言わないとか・・・!?
いずれにしろ、ベックの興味はまた、新たなサウンドの創造と飽くなきギターの可能性追求へと向かっていた。
フュージョン・サウンドの先駆者
75年、付いて来るメンバーがいなくなったのか、はたまた付いて来られるメンバーが見つからなかったのか、ベックはついにソロとなり、全面インストゥルメンタル(=インスト。唄なし)のアルバム「ギター殺人者の凱旋(Blow By Blow)」をリリースした。今ではロック・ギタリストのインスト・アルバムなど珍しくもないが、当時はまだ前例があまり無く、かなり衝撃的なものだった。内容的にも、ジャズ寄りのミュージシャンを従え、ロックとジャズの融合を図った斬新なものだった。
それまでのジャズ・ロックは電子楽器を使ったジャズという感じで、ほとんどが長いインプロヴィゼイション(即興演奏)が主体のものだったが、ベックの生み出したロックとジャズのクロスオーヴァー・サウンドとは、ロック・ビートやファンキー・ビートにのせたジャズ的アプローチで、当時マイルス・デイヴィス一派が推し進めていたクロス・オーヴァー・サウンドに近いものだった。曲もコンパクトでポップ、ギター・プレイに関しても、ジミー・ペイジ(元レッド・ツェッペリン/g)曰く、「ギタリストのための教科書だ」という通り、あらゆるテクニックを駆使した、もうほとんど人間国宝級の職人芸だ(よく聴かないとわからないが・・・)。また、このアルバムにはスティーヴィー・ワンダーの曲が2曲入っているが、スティーヴィーとベックのつき合いはかなり古い。
これは以前「迷信」という曲をベックがスティーヴィーからもらったときに、良い曲だと言うことで、レコード会社が勝手にスティヴィーにもレコーディングさせ、ベックより先にシングルとして発表させ大ヒットしてしまったことがある。その時ベックが激怒したことがあり、そのお詫びにということでプレゼントされたらしい。それにしてもそのうちの1曲「哀しみの恋人達」は名曲だ。それに応えるように、ベックのギターも魂を揺さぶるような最高の音色で感動的に仕上げている。
このベック初のソロ・アルバムは全米4位の大ヒットを記録。インストのアルバムがこれほどのセールスを記録するのはたいへん珍しい。この大ヒットで、それまで3大ギタリストの中では、一番地味な存在であったベックも、一挙にクラプトンやジミー・ペイジと肩を並べるほどの存在となった。
また、このアルバムの成功は、ロック界のみならずジャズ界へもかなりの影響を及ぼし、あっという間にクロスオーヴァー・サウンドは一大ムーブメントを巻き起こす。そして、ついには「フュージョン」という1ジャンルとして独立してゆくまでに発展する。
翌76年、ベックは同路線のアルバム「ワイアード」をリリース。このアルバム、同路線とは言っても、ベック自体はかなりロック寄りのギター・プレイへと戻していて、ファンの中ではフュージョンとは一線を画す、ベック・オリジナルのロック・サウンドだとして、このアルバムをベックの最高傑作に挙げる人も多い。このアルバムも全米16位とかなりの好評を得た。
また、ベックのサウンドには以降大きな変化がないことから、実質この時期にオリジナリティが確立されたと言ってもよいだろう。
この頃のベックはまた、ジャズ・プレイヤーとのセッションやライブ・ワークを積極的にこなし、このことは、多くのジャズ・プレイヤー達にも脚光を浴びさせる結果となった。ヤン・ハマー(key)、スタンリー・クラーク(b)、ナラダ・マイケル・ウォルデン(ds)、サイモン・フィリップス(ds)などがその例だ。
ヤン・ハマー・グループとの全米ツアーは、「ライブ・ワイアー」として77年にリリースもされている。
78年、ベックはスタンリー・クラーク、サイモン・フィリップス、トニー・ハイマス(key)というメンバーで来日。しかし、この頃から急激にベックのプレイは精彩を欠くようになり、しだいに失速してゆく。80年にはサイモン・フィリップスやトニー・ハイマス、ヤン・ハマーらを迎えて、アルバム「ゼア・アンド・バック」を発表するが、明らかにそれまでのような新鮮さが無く、ベック自身にやる気が感じられなかった。おそらくはそれまで自由奔放にさまざまな最先端サウンドへチャレンジしてきたが、ビッグになってしまったことで、イメージを変えるのが難しくなり、周囲の期待に応えるための心の葛藤がかなりあったのではないだろうか。
この年、4度目の来日を果たすものの、その後長い沈黙に入ってしまう。その間には、コージー・パウエル、ティナ・ターナー、スタンリー・クラークらのソロ・アルバムやロバート・プラント(元レッド・ツェッペリン/vo)のプロジェクト、ハニー・ドリッパーズへゲスト参加したぐらいで目立った活動はしていない。84年には一時的にロッド・スチュワートの全米ツアーへ参加するが、すぐに喧嘩別れした。しかし、ロッドとの関係はその後もつづいていたようで、85年久しぶりにリリースしたアルバム「フラッシュ」ではカヴァー曲「ピープル・ゲット・レディ」をロッドと共演。この曲はシングルにもなり、スマッシュ・ヒットを記録している。また、このアルバムはプロデューサーに、デヴィッド・ボウイの大ヒット作「レッツ・ダンス」でお馴染みナイル・ロジャース(元シック)を起用するなど話題を呼んだが、内容はヴォーカルを入れたり、参加ミュージシャンもロッドの他ヤン・ハマー、カーマイン・アピスなど昔馴染みのメンバーで固めるなど懐古的で新鮮みが無く、かなりガッカリさせられた。
この後またもや沈黙し、もはやベックもこれまでかと思われたが、89年突然インストゥルメンタルの意欲作「ギター・ショップ」をリリースして再起を図った。
このアルバムでは、トニー・ハイマスとテリー・ボジオ(元フランク・ザッパ&マザーズ/ds)に曲やアレンジ、リズム関係は完全に任せ、プログラミングを多用しながらも、ベックは久しぶりにトリッキーなプレイをふんだんに盛り込み、やる気に満ちていた。だが、その内容の素晴らしさとは裏腹にチャートでの反応は厳しく、全米49位がやっとだった。あまりにも第一線から遠ざかっていた時期が長すぎたのかも知れない・・・。
90年代に入ると、セッション・ワークを主体に活動し、ジョン・ボンジョヴィ(ボンジョヴィ/g)、ケイト・ブッシュ(vo)、ポール・ロジャース(元フリー〜バッド・カンパニー/vo)、ロジャー・ウォータース(元ピンク・フロイド/vo,b)等のアルバムへ参加したり、93年にはビッグ・ダウン・プレイボーイズとのコラボレーションでジーン・ヴィンセント&ザ・ブルー・キャップスのギタリストに捧げられた異色作「クレイジー・レッグス」を発表したりした。
そして長らく音沙汰も途絶え、引退したのではとの噂もちらほら聞かれるようになった90年代末('99)、なんとオリジナル・アルバムとしては10年ぶりの「フー・エルス!」を突如発表。これには、ただただ、ニュー・アルバムが出てくれただけでうれしかった。内容もなかなかで、しばらく現役を退いていたとは思えない現代風のサウンドで健在ぶりを示した。この年、久しぶりの来日も果たし、その模様はTVでも録画中継された。そのライブでの姿は、とても元気そうで晴れやかな顔つきだったのが印象的だ。往年の厳しい表情とはまったく違っていたが、プレイ自体は昔のまま素晴らしく、多くのファンを大満足させた。しかし、次のアルバムは、また10年ぐらい先だろうと誰もが予想していたはず・・・。
ところが、約1年足らずの2001年早々、早くもニュー・アルバム「ユー・ハッド・イット・カミング」が発表された。しかも完全復調を思わせるバリバリの意欲作だ。
もうすぐ「おじいちゃん」と呼ばれそうな年齢であるにも関わらず、また新しい奏法を模索し、トリッキーで多彩なプレイを連発している。驚くことにベックはこのアルバムで、Fenderストラトキャスター・モデルのギターとMarshallのギター・アンプ以外一切使用していないということだ。
また女性ギタリスト、ジェニファー・バドゥン(元マイケル・ジャクソンのツアー・メンバー)や、女性ヴォーカル、アイモゲン・ヒープの起用は、今のロック界は女性がリードしているという、ベックの鋭いアンテナがとらえたロック界の現状なのだろう。このアルバムに収録されている「ダーティー・マインド」という曲は、2002年のグラミー賞でBest Rock Instrumental Performanceを受賞した。
しかし、これで落ち着いているようなベックではない。2年のインターバルを経て届けられた新作は、アンビエント・テクノやノイズ・ミュージックを意識したバリバリのインダストリアル系サウンド。近年ベックを聞き始めた多くのファンをまたもや失いそうだが、好き嫌いは別として、衰えをしらない創作意欲、ギターにかける情熱・・・ジェフ・ベックがいる限り、ロック・ギターの進化はまだまだ止まりそうもない。(HINE)2005.5更新

JEFF BECK Jul. 2006 スイス/ルツェルンでのライブ
こんなかっこいい写真をファンの方から送っていただきました。なんと会場は自由席で、前から2列目ぐらいの位置から
ライヴを堪能されたそうです。写真もこのとおり撮り放題。なんともうらやましいじゃありませんか!!しかしベック師匠は
60歳だというのに若い!2〜3年前と比べても体が引き締まり、さらに若返った感じがします。腕の筋肉を見てください!!
|






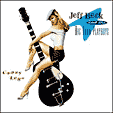
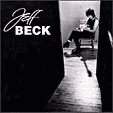


 誰もが認める世界最高のギタリスト
誰もが認める世界最高のギタリスト
