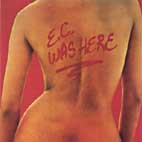|
|
| (HINE) 2002.4 |
 Eric Crapton RSO/Polydor |
 461 Ocean Boulevard RSO/Polydor |
 There's One in Every Crowd RSO/Polydor |
 No Reason to Cry RSO/Polydor |
 Slowhand RSO/Polydor |
 Backless RSO/Polydor |
 Another Ticket RSO/Polydor |
|
ディスコ・グラフィー 1970年 Eric Clapton(エリック・クラプトン)*初めて自ら全曲のヴォーカルをとった、ファースト・ソロ・アルバム |
 Behind the Sun Warner/WEA |
 August Warner/WEA |
 Journeyman Reprise/WEA |
 Unplugged Reprise/WEA |
 From the Cradle Reprise/WEA |
 Pilgrim Reprise/WEA |
 Reptile Reprise/Warner |