Written by ぴー
| LONG LIVE ROCK'N'ROLL 1978年5月発売 バビロンの城門/レインボー Ronnie James Dio(vo), Ritchie Blackmore(g), David Stone(Key), Bob Daisley(b), Cozy Powell(ds) |
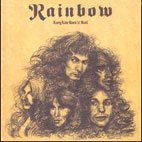 |
| この作品のアルバム・ジャケットは、前2作のそれと比べると、実にシックな構図と色調で仕上げられている。ヨーロッパあたりの、古い城壁の色をイメージしたような、もしくは、アラビアの砂漠の色のような、ブラウン掛かったベージュの台紙に、黒一色でメンバーの顔がラフにデッサンされていて、バンド名、アルバム・タイトル、そして、裏ジャケットのメンバーの名前等も、黒字のゴシック体で書かれている。バンド名のレインボーは、当然七色の虹を意味するのだが、その虹の極彩色とは対照的な、モノトーンに近いこのジャケットは、シンプルであるが故に品の良い風格を漂わせていて、その中に収められているサウンドに対する、大きな期待感を抱かせる。アルバム発売当時は、もちろんアナログLPの時代であった。32cm四方の大きくて、芸術的なアルバム・ジャケットを初めて手にした私は、その中に封印されているはずの、新たなるレインボー・ワールドの幻影に対し、大きく胸をときめかせた。そして、ご存知のようにその封印は、レコード盤に針を下ろすことで、簡単に解かれるのであった。(おおげさで、すみません・・・笑) このアルバムで、前作までバンド名の前にくっついていた、(リッチー・)ブラックモアズという文字が、ついに無くなった。これは、リッチーがレインボーを正式なバンドとして認めた事の表れなのであろうか? 私は、このアルバムを全曲通して聴き終わってみて、サウンドに一貫性が生まれたという事、そして、ミステリアスで、アグレッシブで、芸術性も秘めているレインボーのサウンド・コンセプトが、前作よりもさらにパワーアップし、ここに確立したという事を切に感じた。一説によると、リッチーは、このアルバムあたりから、アメリカン・マーケットを強く意識し始めていたとの事だが、確かに前作に収められていたような、アメリカ受けしない感の有る、長編大作は無くなったが、サウンド自体が、アメリカン・ナイズされている部分は微塵も無く、コンパクトに纏まった楽曲には、贅肉を削ぎ落とした後の、無駄の無い、たたみかけるような凄みと充実感がある。このレインボーのサード・アルバム、『バビロンの城門』に収められている全8曲を一纏めにして考えると、一貫性を備え、起承転結のある、ドラマティックな超大作に仕上っている事が解かる。そして、バンドの演奏はよりタイトになり、総合的にレベルアップしている。リッチーは、自身の確立した、独自性に富んだギター・ワークを、思う存分披露していて、彼のプレイするギター・ソロは、より情熱的になり、芸術性を増している。また、ロニーのボーカルは、(ラストナンバーのバラード以外)終止ハイテンションで、メロディアスな高音部をシャウトし続けるような曲がほとんどで、そのとてつもなくパワフルな歌を聴いていると、こっちの(聴いている人間の)血管が切れそうである。シャウトと言ってもロニーの場合は、それが地声の延長でスムーズに出せるから、これほどまでの迫力をキープしつつ、喉を潰さないのだろう。普通のボーカリストではこうはいかない。コージーのドラムに関しては、少しサウンド処理が前作と変わっている様で、各ドラム・パーツの音が、クリアーで立体的になっている。前作の方が、バスドラによる重低音的迫力は強かったかも知れないが、この作品では、実に心地良い音の切れ味を体感できる。もちろん、彼のずば抜けたドラムセンスは相変らずで、そのドラムワークは、楽曲毎に緻密に構成されていて、全体的な迫力はむしろアップしている。さて、ベーシストとキーボーディストは、予想通り前作のメンバーとチェンジしていて、ベースに関しては、何とアルバム中半分以上の曲を、リッチーが弾いてしまっているようだし、キーボードも、ファースト・アルバム同様存在感は薄い。バンド・サウンドが確立されたとは言え、さらに三頭政治のニュアンスが強固になったわけで、三人以外は、本当の意味のメンバーではないのかもしれない。しかし、結果的にはアルバムの出来は良く、前作同様名盤の域に充分達している。 |
|
| 1. Long Live Rock'n' Roll ロング・リブ・ロックン・ロール ハイテンションなロックン・ロールナンバー。例の、コージーが叩き出すメタルリック・シャッフルが実に心地良い。ロニーのボーカルは、ヘビメタ風に研きがかかり、リッチーのギター・ソロは実にドラマティックで感動的である。明るい様で暗い、レインボーならではの、独創的なロックン・ロールである。 2. Lady Of The Lake レディー・オブ・ザ・レイク メタリックなギターのリフ、シンプルで力強いドラムのビート、どことなく悪魔的な、呪文のようなボーカルのフレーズ、ん?「あっ!いっ、痛い!」オーディオ・セットのスピーカーから流れてくる、この曲のレビューを書いているたった今、曲に合わせリズムを取っていた私の足の裏に激痛が走った。な、なんと床に放置されていた、CDウォークマンのヘッドホーンのプラグ部分が、私の右足の裏(かかとの近く)に斜めに突き刺さってしまっているではないか。やはり、この曲のメロディー・ラインは、呪いのフレーズなのか?(除霊の為)足の裏に十字に2枚のバンドエイドを貼り、かんばって執筆を続ける私である。「しかし、痛すぎる。」 3. L.A Connection L.A.コネクション 脱退したトニー・カレイの事を唄ったナンバーらしい。ミディアム・テンポのリフの上に。ロニーの「これでもか!」と言うくらい、迫力の有る歌声が気持ち良く乗っかってくる。やはり彼の喉は鋼でできているようだ。大怪獣の足踏みのような、重たいビートが大地を揺らす、ボリューム感に富んだナンバーだ。 4. Gates Of Babylon バビロンの城門 私は、この曲がレインボーの最高傑作だと思っている。中近東風の雰囲気を上手くヘビー・ロックに取り入れた、リッチーならではの名曲である。この曲でのリッチーのギター・ソロを聴くと、彼にギターの神が宿っているのを感じる。いや、彼自身が神の域に達してしまったのかも知れない。このプレイについて、リッチー本人が、「今まで自分が演奏してきた中で、最も納得がいくベスト・ギターソロだ。」と、語った事があるらしい。起承転結を踏まえた、スケールの大きなギター・プレイである。 5. Kill The King キル・ザ・キング 「王を殺せ!」なんて、実に過激なタイトルのナンバーである。凄まじいスピード感と臨場感、重厚なアンサンブル、そして、とてもスリリングな曲の展開に、聴く者は、必ず心地良い興奮を覚えるであろう。過激なまでにアグレッシブかつヘビーでいて、美しさをも備えた、実にレインボーらしい名曲である。この曲でも、セカンド・アルバムに収められていた『A Light In Black 』同様、スピード感と重量感を、同時に堪能できる。コージーが叩き出すドラム・ビートは、ハイテンポでも決して軽くならないのだ。 6. The Shed(Subtle)ザ・シェッド 気持ち良く歪んだ音色の、リッチーが奏でるフリー・ギター・ソロから始まるこの曲は、パンクを意識しているとの事で、実にシンプルで、攻撃的なナンバーに仕上っている。リッチーのギター・ソロは、クリーム時代のエリック・クラプトンにも通じる、懐かしい香りがする。ただ、この曲は、3曲目の『L.A Connection』に、とても似ている気がする。 7. Sensitive To Light センシティヴ・トゥ・ライト 3期パープルの『嵐の女』を思い起こさせる、テンポの良いいかしたナンバー。ハイセンスで、印象的なリフを用いた、ライブ感溢れるこのナンバーは、パープル時代からリッチーが表現してきた、ハード・ロックの王道的魅力に富んでいる。ギターの多重録音によるツイン・リードも、随所に現れるシンコペーションも実に心地良く、一見シンプルな様で、リスナーの快感のツボを的確に捕らえる技を、巧妙に多用した秀作である。 8. Rainbow Eyes レインボー・アイズ おそらく、レッド・ツッェペリンの『天国への階段』に影響されたと思われるバラード・ナンバー。意識的なのであろうが、『天国への階段』と比べると、とてもシンプルに仕上っている。このアルバムを1曲目から7曲目まで続けて聴いてくると、全ナンバーの持つあまりにも高いテンションと、ロニーの全身全霊を込めた、とがった波形のボーカルに、攻撃され続けたリスナーは、心地良いのではあるが、そろそろ疲労感に近い感覚をも持ち始める。そこで最後に、ロニーが打って変わったように、甘美な囁くような歌声で、我々を癒してくれるという趣向だ。その意図で、あえて静寂部分のみのシンプルなバラードに仕上げたのかもしれない。たぶんコージーは、この曲に『天国への階段』の後半でのクライマックス・シーンのような部分を設けて、思いっきり感情を込めたドラムを叩きたかった事だろう。キング・クリムゾンのロバート・フリップ風に表現すると、コージーが『レインボー・アイズ』に参加していないという行為は、クリムゾンの『トリオ』における、ビル・ブラッフォードの“称賛に値する沈黙”と同じなのかもしれない。あれ?この曲を聴くと、アルバムの2曲目を聴いている時に負った、私の足の裏の怪我の痛みが、スーっと消えていく・・・、気がする。(笑) |
|
(ぴー) 2004.12